【卒業生インタビュー】
がんが完治した祖父の笑顔が脳裏に。 患者さんに寄り添える医師になりたい
インタビュー
M.Aさん SAPIX中学部 高田馬場校→学芸大附高→千葉大学医学部医学科6年
学芸大附高に進学したM.Aさんは現在、千葉大学医学部医学科6年で、医師への道を着実に歩んでいます。
Aさんが医師を目指そうと思ったきっかけや大学での学び、さらには医師として働くための就職活動などについて伺いました。

Aさんが実際に使っている白衣と聴診器
- 2025年6月に取材を行いました。
全てはSAPIXから始まった。クラスの仲間が良い刺激に
――臨床実習でお忙しい中、取材をお引き受けいただきありがとうございます。AさんはSAPIX中学部高田馬場校に通われていたそうですね。
M.A 塾探しの一環で、高田馬場校を訪ねた際、説明してくださった数学の青木先生(当時)※のクレバーさにほれこんだ母は「ここしかない」と即決。
私は中2までに中学の履修範囲を全て学び終えるハイレベルなカリキュラムに魅力を感じました。数学の授業を受けてみると、青木先生の鋭く適切な指導が私には合っていて、数学がますます好きになりました。
しかも、クラスの仲間は優秀な方ばかり。一緒に勉強をしていると良い刺激がもらえるので、受験勉強が楽しくてならず、時間さえあれば校舎で自習していました。勉強をしているのに、くつろぎ感もあるくらいで、高田馬場校にはとてもなじんでいたように思います。
- 青木 茂樹…SAPIX中学部教務部長・数学科教科長/『高校への数学』執筆者
――スランプはなかったのでしょうか。
M.A スランプはありませんでしたが、模試の偏差値で38を取ったこともあるくらい、国語が壊滅的にできませんでした。センスの問題だと思い込んでいたのですが、国語の先生が国語の長文問題には論理的な読み解き方があることを教えてくれたのをきっかけに開眼。国語の授業ではその先生に張り付いて質問をし、記述問題の添削をしていただきました。
しかし、私の覚えが悪く、とんちんかんな受け答えをしてしまうことも。国語が足を引っ張っていることが分かっていたので、しがみついてでもやるしかないと思って頑張りました。すると、テストの点数は飛躍的に伸びていきました。
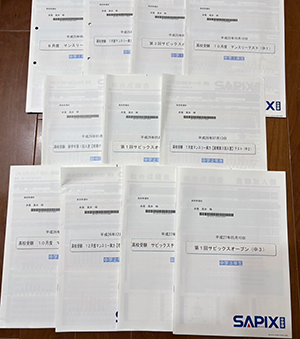
SAPIX中学部のテストの成績表(テストの名称は当時のもの)。たくさん受けて鍛えられました
――学芸大附高を志望校に決めたのはいつごろですか。
M.A 中2の夏の学校見学会で、自由な校風と、先輩方が学校行事や部活に全力投球している様子に一目ぼれ。その帰り道、「私はこの学校に入って、高校生活を思いっきり楽しみたい」と母に宣言していました。
ただ、附高の入試は5教科にもかかわらず、理科と社会は受講していませんでした。そこで理科の先生に相談すると、「まずは自分で勉強し、ベースを作ってから受講した方がいいだろう」と、アドバイスをいただきました。私は自分のペースで自習を進め、分からない箇所は先生に質問し、基礎的な知識を身に付けた上で中3春から理科と社会の受講をスタート。そのおかげで授業にはスムーズに合流できました。
私の性格や現状を見抜いた上での先生のご判断には感謝しかありません。
――受験直前期はいかがでしたか。
M.A 模試はA判定だったので、先生方からは「いつもどおりやればいい」と言われていましたが、実はかなりのプレッシャーを感じていました。
私は幼稚園からずっとお茶の水女子だったので、内部進学をする道もありましたが、退路を断って外部受験を選びました。ですから、それに見合う高校に合格しなければという思いが不安を呼び起こしていたのです。先生方はそんな思いも受け止めて、私をサポートしてくれました。
国語の先生は「ここまで仕上がったから、あとはへまをしなければ大丈夫。でも、ちょっとだけ心配だなぁ(笑)」などと冗談交じりのアドバイスで、私の気持ちを和らげてくれました。
私が附高に合格できたのはSAPIXを選んだからだと思っています。
――Aさんが医学の道に進もうと思ったきっかけをお聞かせください。
M.A そもそも幼い頃から数学や理科が好きで、理系の職業に就きたいと考えていました。
高2になって自分の進路を深く考え始めた時、祖父が膀胱(ぼうこう)がんに侵されました。幸いにも早期発見できたので、膀胱を全摘して完治。ただ、ストーマ(人工膀胱)という袋を体の外に着けることになりました。私はそのことに非常に驚き、そこで初めて医学に興味を持ったのです。また、がんが完治した祖父の笑顔を見て、医師の仕事の素晴らしさを痛感し、医学部への進学を決意しました。
――千葉大学医学部医学科を志望したのはなぜですか。
M.A 「自宅から通えること」を条件に候補を絞った結果、都内の私立大学と千葉大学が残ったのです。私立は学費が高いのですが、両親からは「学費は何とかする」と言ってもらえました。これで精神的に少し余裕ができました。
――SAPIX中学部での学びは大学受験でも役立ちましたか。
M.A はい。例えば、大学受験でも国語が苦手でした。しかし、附高合格のために国語の先生に伝授してもらった、文章を論理的に読み解き、要素を抽出して選択肢を吟味するという解法は、大学受験のセンター試験(現 大学入学共通テスト)でも大いに役立ちました。
本格的な医学の学びは2年から。CBT合格後に臨床実習へ
――念願の医学部に入学されていかがでしたか。
M.A 医学部の定員は1学年約120人で、他学部よりも人数が少なく、基本的に全員が同じ授業を受けます。ただ、私の入学時はコロナ禍だったので、1年の時はほとんど大学に通えず、オンラインで受けました。2年からは対面で行われましたが、授業や実習にはかなりの制限がありました。
――医学部での学びを具体的に教えてください。
M.A 1年の時は自分で選択した一般教養科目が中心でしたが、2年から専門科目の座学が本格的にスタート。まずは生理学で体の仕組みを学びました。高校では物理を選択していたため、私にとって生物分野は難しく、最初のうちはついていくのが大変でした。
2年の後期には解剖実習があり、初めてご献体を前にした時の気持ちは今でもはっきり覚えています。これまでに経験したことのない厳かな緊張感は一生忘れられないでしょう。
3年の後期になると診療科ごとの授業が始まり、病気の原因や具体的な症状、治療法などを一連の流れで勉強します。この頃から医学は面白いと思うことが増えました。
心臓や肺の病気は高齢者や喫煙者がなることが多いですが、婦人科の病気は女性なら誰でも起こり得ます。自分が女性ということもあり、特に産婦人科領域の婦人科疾患に興味を持ちました。
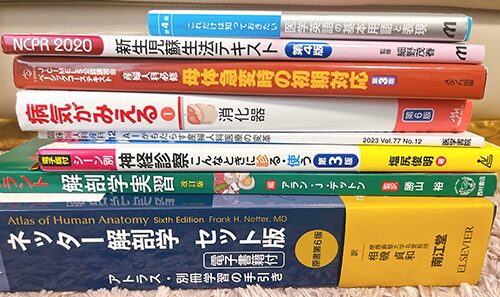
専門書は最近、電子化が進んだので見た目には少ないのですが、実際にはこの数倍の教材で学んでいます
――4年になると臨床実習も始まります。
M.A 臨床実習は、CBT(Computer Based Testing)と呼ばれる医学生共用試験に合格した後、4年の冬から6年の秋にかけて行われます。全部の診療科を数週間ずつ回って、指導医の外来や手術などを見学するため、このタイミングで自身の専門科を決める人もいます。私は新生児科にも興味が出てきて悩んでいるところです。
――CBTは医学部生にとっての一つの大きな山ですね。
M.A 相当前からこつこつ勉強する人もいます。私は部活中心の生活を送っていたので、CBTの1カ月前から焦って勉強し始め、必死に知識を詰め込んで、何とかクリアしました。
――実習先はどうやって決めるのでしょうか。
M.A 大学から指定されます。中心は大学病院ですが、関連病院に短期間、実習に行くこともあります。千葉県内は千葉大学の影響力が強く、県内の大きな病院はほぼ千葉大学の関連病院ですから、そういった所に派遣されます。
卒業後2年間の初期研修先は希望を擦り合わせてマッチング
――医師にとってのいわば就職先である、卒業後の初期研修先は自分で決めるのですか。
M.A 他学部の就活は学生が自らエントリーした企業から個々に合否連絡を受けると思います。医学部はそうではなく、全国の医学部生と2年間の初期研修を行っている病院の両方を医師臨床研修マッチング協議会が全て統括。医学部生はエントリーしたい病院に履歴書を送って面接などの試験を受けた後、勤務したい病院の希望順位を協議会に提出します。
病院も採用したい学生の希望順位を連絡し、協議会が学生と病院の希望を擦り合わせて、学生の研修先(就職先)を決めていくのです。全国の医学部生の就職先が一斉に決まるので、私たちはこれをマッチングと呼んでいます。
いくつ受けるかは学生それぞれですが、人気の高い都内の病院を希望する場合、7〜8カ所は受けると思います。ただ、医師マッチングは履歴書で切られることがほとんどなく、地域によっては是が非でも医師がほしいと思っているので、場所を選ばなければ就職できないことはありません。
――初期研修先の候補はいつごろから探し始めるのでしょうか。
M.A 5年の春ごろからです。とはいえ、病院はとてもたくさんあるので、選ぶのは本当に大変です。ほとんどの人は5年の夏に行われる合同説明会に参加し、そこから徐々に絞っていって、5年の秋くらいから病院見学を始めます。希望する病院に事前に連絡し、日程を調整して、自分が希望する診療科を1日見学させてもらうのです。
現時点での私の第一志望は産婦人科であるため、病院に産婦人科があることが最低条件。卒業して1〜2年目の初期研修医は未熟なので、戦力にならないことが多いのですが、それでもそんな私たちに仕事を振ってくれる病院を探しています。
医学部の履修期間は6年間なので、部活の先輩が大勢います。先輩方はさまざまな診療科に進んでいますから、病院選びや病院見学の貴重なアドバイスをしてくれます。医学部では縦のつながりが重要とよくいわれますが、それを得るために部活に入る人もいるほどです。
ヨット部の練習に心血を注ぎ、セブ島で医療ボランティアに参加
――Aさんも部活に入りました?
M.A 新しいことに挑戦してみたいと思い、ヨット部に入りました。中学はテニス部、高校は水泳部でしたが、どちらも経験者が多いですよね。私は初心者で始めたので、最初から後れを取ってしまいました。そこで、大学ではほぼ全員が初心者で始めるスポーツをやりたいと思ったのです。その点、ヨットなら経験者が少ないですから。
ヨットは夏がシーズンのスポーツなので、5月から毎週末は江の島で朝8時から夜9時くらいまで練習し、8月には2週間の合宿もあります。千葉大学医学部ヨット部はコロナ禍前に東日本医科学生総合体育大会(東医体)で2連覇したものの、その後の成績は振るわないので、部員は練習に心血を注いでいます。

私がエントリーする470(よんななまる)級は男女混合で競います。頭脳戦の要素も大きく、繊細さも求められるので、女性でも活躍できるのが醍醐味です
――勉強と部活の6年間だったのですね。周りの皆さんも同じような学生生活を送っているのでしょうか。
M.A 千葉大学医学部で、ヨット部は女子が所属できる部活で一番ハードだといわれています。部活ではなく、留学や研究に打ち込む人も結構います。私も部活を引退してから学会に参加し、5年の2月には2週間、フィリピンのセブ島の地方の病院でボランティアをしてきました。
――そういったプログラムは大学が用意してくれるのですか。
M.A 大学が用意してくれるプログラムはかなりあり、そうしたものに参加する人が圧倒的に多いです。でも、私は途上国での医療を経験したかったので、自分で医療ボランティアを探して参加しました。

手術室の見学や分娩の介助など、セブ島では日本での実習よりも踏み込んだことまでさせてもらえたので、とても勉強になりました。写真は分娩室(DELIVERY ROOM)の前で
――ところで、初期研修終了後は、そのままその病院に勤務するのでしょうか。それとも別の進路も選べるのでしょうか。
M.A 初期研修を受けた病院にそのまま残る人もいれば、母校の大学病院に戻る人もいます。あるいは、初期研修を受けた病院とは別の病院に勤務する人も珍しくありません。
また、進みたい診療科を絞り込み、専門研修プログラムを実施する医療機関で3〜 5年間の専門研修を受ける人もいます。ただ、外科や内科なら専門医の認定が取れる病院は多いのですが、私が興味を持っている産婦人科は特殊性が高いため、千葉県内で対象となる病院は限られます。
その他、地方から進学した人は地元に戻ることもありますので、初期研修終了後の進路はかなりばらばらです。
――マッチングのために多くの病院を見学し、面接などを経てやっと決まった初期研修の病院に勤務しても、その先をまた探さなくてはいけないこともあるのですね。
M.A もちろん、初期研修先で一生働くつもりで、最初からかなり大きな病院を条件にしてマッチングに取り組む人もいます。私は産婦人科に強みを持つ病院を探しているので、その病院で専門医の認定が取れれば、改めて探す必要はありません。
しかし、私は初期研修が終わってからのことよりも、初期研修2年間のプログラムがどのくらい充実しているかをポイントにしています。というのも、2年間のうちに幅広い診療科で多くの経験を積み、医師としての基礎固めをしたいからです。
――将来はどのような医師になりたいと思っていますか。
M.A 産婦人科の臨床実習で妊婦さんの笑顔や安心した表情からたくさんの元気をいただきました。一方で、妊娠は病気ではありませんが、不安や痛み、体調不良がつきまとうもの。外来で涙を流されていたり、不安な気持ちを先生に相談されていたりする様子も見てきました。
将来、どの診療科を選んでも、患者さんときちんとコミュニケーションを取り、不安や心配事を聞き出し、心に寄り添える医師になりたいと思っています。
――後輩に向けてメッセージをお願いします。
M.A SAPIX中学部で鍛えていただいた数学や理科の力は高校時代にかなり生きたと思います。高校の授業を受けていて「これ 、サピで学んだな」ということがよくありました。また、前に述べたように、国語の論理的な読み解き方については大学受験でも十分通用しました。そんなふうに実感することは医学を学修する現在でも変わりません。SAPIXで培った学力は一生ものになります。
しかも、SAPIXの先生方は本気で指導してくださいます。時には大変なこともありましたが、それを乗り越えたからこそ今があります。一心に机に向かうことで培った集中力、何が何でも理解するぞという粘り強さは、患者さんの命を預かる医師になってからも私の仕事を支えてくれるものと自負しています。
SAPIXの先生方を信頼し、志望校合格に向けて頑張ってください。
